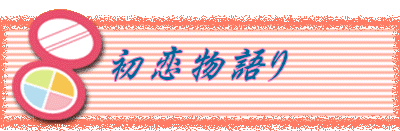
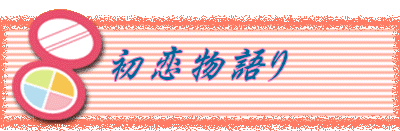
午前八時二十分、始業時間十分前だ。ラジカセから流れてくるラジオ体操の声に合わせて、皆が体を動かし始める。ご苦労なこった、と思いつつ俺もだ。まったくかったるい。 「おい、そこ。キビキビとやりなさい!」 ジョーダンじゃねぇぞ。くそ、もう辞めてやる! 俺は今、仕事に嫌気がさし始めているんだ。何でかって、それは…。一番の理由は、仕事で使う車が軽自動車だということだ。出足・加速・クッション、全て最悪だ。全く腹が立つ。何だそんなことかなんて言われたくない。ほぼ一日を車で過ごしてる身にもなってほしいぜ。その上に車の乗り方で、会社の上役に小言を言われてもいるし。 「もう少しおとなしい運転をするように! お前だけガソリン代が多いじゃないか!」 交差点で隣の車が俺を煽るから、ついつい『ゼロヨンスタート』の真似事をしてしまうせいなのだ。もっとも他の者は、出足とか加速とかに興味がないらしい。走れば良いという輩ばかりだ。だからガソリンも喰わないし故障も少ない。そのうちの一人が、嫌みたらしくこう言う。 「君がいくら頑張って走っても、信号というものがあるのだから大した差は出ないだろうに。そんな無駄なことに神経をすり減らすより、もっと気楽に行こうよ。それに、そんな無謀運転をするからポリスさんに切符を切られるんだよ。反則金がもったいないし、免停にでもなったら大損じゃないか。」 そこで、俺はいつもこう言ってやる。 「俺はネ、他の車より先に目的地に着こうなんて思っていない。グンとアクセルを踏み込むだろ。スピードメーターがグーンと伸びる。すかさずギアをセカンドにチェンジ。すると、横から普通車がグーンと出てくる。相手はまだローだ。そこで俺は又踏み込む。エンジンが悲鳴を上げる。30キロだ、針がそこを指すと、すぐさまサードにチェンジ。針が伸びて40〜50キロになる。そこでトップにギアを入れ、アクセルをゆるめる。分かる? ここのところの気持ち。スカッとする瞬間だ。」 得意満面で答える俺に、突然の冷や水だ。 「で、どうなの。その普通車に勝つのかい?」 「分かってないな、勝てる筈がない。いつも抜かれてるよ。相手は普通車だよ。加速力が全く違うんだぜ。同じ軽ならと言いたいけれど、全戦全敗です。M社の水冷エンジンはきつい、重いもの。他のメーカーは空冷だしね。だけど、フロアシフトのギアは良い。シフトの動きが良い。GT感覚だよ、実に小気味いい。その点、コラムシフトだと、こうは行かない。ガツンがガフンだもの。力が入らないネ、まったく。」 「君の心理は分かんない。反則金に免停だよ、そんな大きな代償を払うようなものかね。」 「フン、あんたのような安全運転の模範生じゃダメだ。この気持ちが分かる筈がない。第一、後ろの車の迷惑だ。ノロノロすぎる。追い越しなんかで、意地悪されないかい?」 「そんなことはないさ。ちゃんと、交通法規通りに走っているんだ、大丈夫だよ。」 「あぁもう、ホントに分かってない。法規なんて、破る為にあるんだぜ。誰も破らないんだったら、作る必要がないじゃないか。それにポリスという職業がある以上、誰かが違反しなきゃ。そうでなかったら、ポリスさん達おまんまの食い上げだ。」 「そんなこと、君が心配することはないサ。」 「我々青年はだ、…、やめた。あんたにこんなこと言っても始まらない。」 俺は諦めた、この無気力な男には何を言っても無駄だと。人生観が違いすぎる、と。 「オーイ!そこの二人。配達だ、早くしろ。」 気まずい空気が流れかけた時、はかったように声がかかった。 「君、Aルートの益田商店に行ってよ。あそこの娘さん、君の方が良いらしい。この間届けたら、淋しそうだったよ。」 と、とんでもないことを言い出した。 「えっ? この俺に。冗談も休み休みに言えよ。俺は知らんぞ、そんなこと。」 口をとがらせつつも、内心では嬉しかった。主任から伝票の束を受け取り、車に向かった。念のために、ラジエター水の確認、ガソリンもOK。キーを回しエンジンの機嫌を伺う。よし良い音! 上々だ。さぁ、出発だ! ギアをローに入れ、勢い良くスタートした。苦笑いの彼をバックミラーに見ながら、いつも通りセカンドからサードまでグイグイ引っ張った。 角を曲がりきると、20キロに落ちている。このままトップに行くと、加速が弱いこの車ではヨレヨレになってしまう。ぐっとアクセルを踏み込む。物凄い唸り音を立ててスピードがグングン伸びる。30そして40キロ、ストップだ。アクセルから0,5秒の素早さでブレーキに足をかけた。平均では0,7秒らしいが、いつも急ブレーキの練習をしている俺は、やはり早い(筈だ!)。 3ナンバーの大きな車のテールランプが点いている。やむなくストップした。しかし、何で止まっている? イライラが頂点に達した時(3秒かな? 待てるのは)、クラクションでせっつこうとしてやめた。信号が赤だ、全くしまらない。 3ナンバーが、静かにタイアを軋ませることもなく出て行く。俺は急いで、グンとアクセルを踏み込んだ。そしていつものように忙しなくギアチェンジを繰り返しながら、車の尻を叩いた。が、ギアがトップに入った時には、彼の車は次の信号を渡り終えている。なんと情けない。声が出なかった。しかし考えてみるに、3,000ccの大型車と同じ加速を360ccの軽自動車に望むのは所詮無理である。生まれたての赤ん坊に、高校生との100m競争で勝て! と要求するが如きものだ。富士山をつるはしで崩せ! ということである。俺はそう考えることで、ようやく自分の気持ちを落ち着けた。 益田商店に着いた。配達物を持って、ゆっくりと大股に入って行く。狭い店の中で、皆忙しそうに働いている。 「毎度!」と、大声で怒鳴るように叫んだ。 「あぁ、ご苦労さん。」と、部長が仏頂面で答える。俺は、いつものように二階へ運ぶ。そしてその二階には、俺に気があるらしい女性がいる。少し胸をときめかせながら上った。 そして又、 「毎度!」と怒鳴る。二度も同じ言葉を発して何をくだらぬことをと思いつつも、いつもそうしている。要するに、「毎度」以外の気の利いた言葉が出てこないのだ。主任からは、お世辞の一つも言ってこいと言われてはいるが、どうにも言葉が出ない。まだ十八歳の若造が、二まわりも年上のおっさんに対して 「昨夜の戦果は如何でした?ゴルフは如何でしたか?」などと言えるわけがない。夜の戦果の意味するところすら、正確には知らない。主任は、そう言えと言うのだけれど。 「配達の折に注文の一つも貰って来い、たまには。」と言われた。冗談じゃない!その分の給料は貰ってないぞ。でいつもなら、 「ご苦労様!」と返ってくるはずが、今日に限って何の返事もない。階段の途中で、鎌首をもたげて覗き込んだ。一望できる仕切りのない作業場には、誰も居ない。返事が返ってこないわけだ。 仕方なく、窓から外の景色を眺めた。相も変わらず忙しそうに、車が行き交いしている。車の保有台数は、全国で三番目だと聞かされている。実に多い。この車の台数を半分に減らそうものなら、確実に事故が増えることだろう。断じて減ることはない。俺は確かにそう思った。その理由に、車が多いからこそ緊張し、車が多いからこそこれ以上のスピードが出せない、そう思った。 「ホント、車が多いわね。半分くらいに減ったら、事故も減るでしょうに。」と、突然あの彼女が俺に囁くように言ってきた。俺は、背筋に水が流れるようにヒヤリとした。 「そ、そうですね。」 何と言うことだ。実に情けない。裏腹のことを答えてしまった。自分に腹が立った。しかも、卑屈にもうろたえてだ。昨日までは何も意識していなかった彼女の存在が、今はドギマギさせる。伝票にサインをもらうと、それ以上の言葉を交わすでもなく、そそくさと店を出た。 空はカラリと晴れ渡っている。何故か、車に乗ることに嫌悪感を感じた。といって、歩いて帰るわけにもいかない。車のエンジンをかけるが、どうもエンジン音が気になる。ついさっきには感じなかったことだ。そのまま出ようと思ったが、どうにも気になる。ボンネットを開けることにした。ひょっとして、彼女が外に出てきて 「どうしたの?」と声をかけてくれるかも?と、馬鹿な思いが頭を掠めた。 冷却水もオイルも、やはり異常はない。エアークリーナーを見る。異常なし。二・三度スローバルブを引き上げて空吹かしをしてみる。少し、スローが高いような気がする。しかし、下げるわけにはいかない。下げれば、ガソリンの消費も少しは減り、エンジン音も幾分かは静かになるだろう。しかし、下げるわけにはいかない。おとなしいエンジンになってしまう。それだけは、許せない。俺のポリシーに反する。じっと、腕を組んで考える。そして思い出した。ガソリンスタンドで、 「タペットが悪いかも?」と言われたことを。 「そうかなぁ。」と答えはしたものの、そのタペットの位置を知らない。いや、タペットそのものを知らないのだ。同年代の男に聞くのは嫌だ、我慢ができなかった。 結局のところ、彼女は出てこなかった。彼にからかわれたのかもしれない。それとも仕事中のことだ、外を見ていないのかもしれない。どちらにしろ、裏切られたような思いを胸に車を走らせた。 店に戻って、主任に車の異常が気になると報告してみた。 「あの、主任。車の調子がおかしいんで、見てもらっていいですか?エンジン音がうるさいんです。」 「あぁ、音だ?お前さんの運転ではうるさいわな。静かに走ればいいんだよ。」 「それにですね、ブレーキの効きも悪いんですよ。サイドブレーキも弱いですし。」 「いいから。そんなことは車だけに頼らずに、自分の自慢の腕でどうにかしろ。急ブレーキをかけなきゃいいことだし、サイドにしたってギアをローに入れておけば問題ない。」と、予想通り相手にしてもらえなかった。 ”ケッ、何とまあ調子のいいことを。自分の腕でカバーしろだって。いつも『人間の勘とか腕だとか、そんなものに頼ってはいかん。おかしいと思ったらすぐに報告するように』なんて、いつも言ってるじゃないか。“と腹の中で愚痴りながら、思いっきり舌を出してやった。 「又叱られたわネ。」 「フン、叱られたっていいさ。俺は悪くない。ところで、今日は土曜日だよね?」 「そうよ。明日は、日曜日。」 「そうか、よし。明日は車を借りて、ドライブにでも行くか。」 どうにも女性との会話が苦手な俺だ。なのに、三歳ほど年上のこの女性事務員とは苦にならない。 「ねぇ、私も連れてってよ。そんな怪訝そうにしなくていいの。私だけじゃなく、もう一人いるの。今度入った娘よ。一人では恥ずかしいから、三人でのデートをしたいんですって。この、色男が!」 突然のことに、何と返事をしていいのかわからず、唯ドギマギして口ごもってしまった。それにしても、今日はどういう日だ。二度も三度もドギマギさせられるとは。 「じゃあ、明日十時に会社の駐車場ね。そうそう、車の事は私から頼んでおくから。じゃ、そういうことで、キマリ!」 一方的に取り仕切られて終わった。自分の行動を他人に仕切られるのは嫌なのだが、今回は妙に嬉しい。自分で決断できなくても、腹が立たない。すでに頭の中では明日の走るコースを色々と思いめぐらせていた。 正直の所、デートなるものを一度もしたことがない。硬派を自負している俺ではあるが、まるで興味が無いわけではない。否、むしろ悶々とすることが多いかもしれない。 新入りの娘は、一週間ほど前に入った夜学生である。結構かわいい娘で、少々気にはなっていた。しかし例の如く話しかける勇気もなく、遠くから唯見ているだけだ。確か、十六歳のはずだ。親元を離れての、集団就職だと聞いた。初めの職場では人間関係がうまくいかず、学校の斡旋でこの会社に入ってきた筈だ。社長の娘であるこの事務員が、お姉さん代わりに何やかやと世話を焼いている。 その社長令嬢に対して、俺はため口を利いている。他の者は、結構敬語を使っているけれども。俺に忠告する人もいるが、そうなると反骨心がムラムラと湧いてくるのだ。 |
| 日曜日、カラリと晴れ渡った。俺の前途を祝福しているようで、唯々嬉しい。いつもだとお昼近くまで白河夜舟のくせに、今日は何と七時に目が覚めた。現金なものだ。朝食もそこそこに、会社の駐車場に急いだ。昨日、しっかりとワックスをかけてはいたが、約束の十時までには一時間もある。もう一度、ワックスをかけることにした。勿論、エンジンの点検やら車内の掃除も念入りにした。 車がピカピカに光り始めた。十時少し前を、最新型の腕時計が指している。自慢の物だ。少々高かったけれども、どうせ買うなら、やっぱり良いものをと思ったのだ。この時計を眼鏡店で買ったことに対し、友人が歯ぎしりしていた。俺だって○兵が安いということは知っている。しかし、その時に考えたのだ。安く買うという事は、小売に問屋そしてメーカー全てで利潤を圧迫する。社会全体に利潤がなくなり、巡り巡って俺の勤める会社の利益低下を招くだろう。そして給料に影響してくる。だから○兵はやめた。と、言い張った。実のところは、その眼鏡店に美人の店員が居ると、噂に聞いたからだけれども。 「お待たせー!」 ピンと緊張の糸が張る。次の瞬間、ガクッときた。一人、あの社長令嬢の事務員だけだ。 「心配しないの、真理子ちゃんはお買い物中。お弁当は作ったけど、デザートの果物が欲しいんですって。あそこのスーパーで待っている筈よ、心配ないって。」と、苦笑しながら車に乗り込んだ。 『ガキッ。』と、力一杯にローにギアを入れた。アクセルを踏み込み、出発。暖気運転はしっかりとしている筈なのに、朝一番のエンジンは機嫌が悪い。少しもスピードが出ない。俺は不本意ながら、チョークを一杯に引いた。エンジンが急激に元気になり、スピードが乗った。ところが少し走ってすぐにエンスト。吸い込みだ。 「何、どうしたの?下手なのね、もっとスムーズに運転してよ。点数、下がるわよ。」 “あんたの体重のせいだよ。”と、心の中で思いつつも 「はいはい、お言葉通りにしますよ。」と、答えてしまった。ニュートラルに戻して再始動。又、エンスト。ギアがサードだった。相当上がっているようだ。クスクス笑いの中、俺は気を取り直して再発進した。 ラジオのスイッチを入れると、♪恍惚のブルースよー♪と、流行りの歌が流れてきた。交差点での信号待ちで、ボンヤリと行き交う人を見た。色とりどりの服装かと思ったが、意外なことに殆ど寒色系の色ばかりだった。してみると、俺は黒が好きでズボンにジャンパーが黒で、ポロシャツがモスグリンでは、まるで目立たない。安心できるような淋しいような、変な気持ちだ。そんなおセンチな気分に浸っている俺に、女神が微笑みかけた。 「ごめんなさい、お待たせしました。」 横断歩道で車の窓を叩いてくる。スーパーの駐車場はすぐそこだ。まさか交差点での乗り込みとは考えていなかった俺は、慌てて 「駐車場に入るから。」と、合図した。意外にせっかちなんだ。 俺の意に反し、真理子ちゃんは後部座席に座った。が、内心ホッとする気持ちもある。そんな俺の気持ちを察してか、 「あとで席を交代するから、今は我慢しなさい。」と、事務員からのありがたいお言葉があった。 「そ、そんなこと。べ、別に・・・」と、しどろもどろになってしまった。真理子ちゃんも又、耳たぶまで真っ赤になっていた。 「よーし、行くぞ!」と、グンとアクセルを踏み込んだ。この車にしては、順調に滑り出した。期待通りにスピードが乗ってきた。なのに、冷たいお言葉が聞こえてきた。 「遅いわネェ、もっと出ないの!」 「そんなご無体な!これ以上エンジンを回したら、壊れちゃうよ。」 どういう訳か、事務員とはスムーズに会話ができる。異性という意識がないせいだろうか?それとも、視線が合っていない為だろうか?信号待ちに入ったところで、意を決して真理子ちゃんに声をかけてみた。 「真理子ちゃん、どこか行きたい所ある?」 「どうしたの、声が裏返ってるわよ、フフフ。そうそう、ドライブウェイに乗って。私、プラネタリウムに行ってみたいから。」と、事務員。俺は咳払いをした後、声を整えてからぞんざいに答えた。 「お姉さまには聞いてません。そちらのお嬢様にお聞きしたのですが。」 「アラ、失礼しました。どうせ私は、お刺身のつまでございます。お邪魔虫でございますわ。」と、軽く受け流してくれた。車中に笑い声が起こり、俺は事務員さんに感謝した。これからは感謝の意味も込めて、さん付けにしよう。 「真理子お嬢様、そこでよろしいですか?」と今度は無事に聞けた。 「はい。まだ行ったことがないですから。」と、蚊の鳴くような声で答えてくれた。身震いするような、可愛い声だ。くぅー! 「OK!」と答えるや否や、町の外れにある、さほど高くはない山に作られたドライブウェイに向かって車を走らせた。その山頂を造成し、プラネタリウムが作られている。このドライブウェイは、以前に二、三度走ったことはあるが、プラネタリウムには入ってはいない。山頂の駐車場で一休みしてすぐに下りるだけだった。 市街地を何事もなく無事に過ぎ、ドライブウェイのある山の麓にたどり着いた。二人の訝る視線を背にしながら、俺は車を降りた。念のために冷却水の確認をしたかったのだ。今朝確認をしているので心配は無いのだが、クネクネとした山道を上るのだ、しかも三人で。恥をかくわけにはいかないのだ。 冷却水の確認では、苦い想い出がある。免許を取って間もない頃だったが、水温が異常に上がりオーバーヒート寸前になったことがある。ラジエターの蓋を開けた時、熱湯というよりも火に近いものが俺の顔面を襲ってきた。その時もし、サングラスをしていなかったら・・・背筋が寒くなる。鼻のてっぺんと(短い!)鼻の下と唇とを火傷した。勿論、サングラスは使い物にならなくなった。ファンベルトが半分切れかけになっていたのだ。で今回は少し時間をおいてから、ファンベルトのたるみの確認と冷却水の量の確認をした。 「あまり飛ばさないでね、ヒヤヒヤしたわ。さっき、ダンプカーの大きなタイヤにもう少しで当たるところだったわよ。ホント、生きた心地がしなかったわ。ねえ、真理ちゃん。」 身振り手振りで後ろの真理子ちゃんに話しかけ、同意を求めていた。真理子ちゃんは、さ程に感じていないようだったが 「はい?えぇ。」と、短く答えていた。確かに、助手席では恐怖心が倍加されるだろう。そう言えば、途中から事務員さんのおしゃべりが止まっていた。 「ハイハイ、分かりました。どうせ、上り坂ではスピードは出ません。ご安心下さい。」 三人乗りの状態では、スピードを上げたくとも上がらない。ギアはセカンドのままで、“ウィン、ウィン。”と苦しがりながら、坂を駆け上がっていく。 「右を見てみなよ。」と、二人に告げた。真理子ちゃんが 「えぇっ、すごい!高いわぁ。きれーい!」と、感嘆の声を上げる。俺は、心の中で ”それ以上に君の方が素敵だよ。“と呟いた。と、何かしらマシュマロのような柔らかい物を肩に感じた。 「ホントだ、素敵!来て良かったわねぇ。」と、事務員さんが俺の肩越しに覗き込んでいた。どうしたものかと考えあぐねていたが、残念なことに、事務員さんはすぐに席に戻ってしまった。 “キ、キイィィ!” 事務員さんに気を取られている間に、前の車が眼前に近づいていた。ホッとため息を吐く俺に、容赦ない罵声が浴びせられた。 「こらっ!お嫁に行けなくする気か!それとも、婿養子に来るか?」 「ごめんなさい・・それだけは、ご勘弁を!」 「それだけは、って、どういう意味なの!はいはい、真理子ちゃん一途なのね。」と絶妙のお言葉。姉御肌の事務員さん、ほんとにありがとうございます。あれ?何の花だろう、いい香りがする。前のめりになった真理子ちゃんの匂いか?いい匂いだ。 「あぁ、びっくりした。」 「ごめんなさい、もう少しで頂上に着きまーす。」 駐車場は満杯の状態だったが、幸いにも一台の車が目の前で発進した。幸運に感謝しながら、 「日頃の行いがいいからすぐに止められたよーん。」と、軽口を叩いて止めた。 「何を言ってるの、二人の乙女のおかげよ。」と、事務員さん。真理子ちゃんも、 「そうそう。」と、少しうち解け始めていた。 プラネタリウムの中では、事務員さんが気を利かせてくれた。真理子ちゃんを中央にして、俺を隣り合わせにしてくれたのだ。気恥ずかしさが少し残ってはいたが意を決して話しかけた。 「俺の運転、恐かった?」 真理子ちゃんは何も答えてくれなかった。薄暗い灯りの下で、じっと俯いている。しかし、少したってから口を開いてくれた。 「私、こんなことを、ご本人に向かって言っていいのかどうか分かりませんけど。でも、やっぱり言います。でも、気を悪くしないでくださいね。私、自分が不良のように思えるんです。無茶な運転の車に乗っていたり、暗いプラネタリウムに入ってみたり、で。」 俺は少なからずショックを受けた。不良?しかしつらつらと考えてみるに、そう思われるのが当たり前のような気がする。と、事務員さんが助け船を出してくれた。俺を弁護してくれた。 「そうね、不良よね。でも、そこらの不良とは違うわよ。真面目な不良ってとこかしら。スネてるのよ、この子。根は真面目なの、私が少し悪のりさせたみたい。だってね、パチンコはやらないし、成人向け映画のエッチな物も見ないし・・・」 「ストップ!そこらでいいよ。何ザンスか?真面目な不良とは。」 俺はわざと大げさにおどけてみせた。事務員さんは失笑したが、真理子ちゃんは笑ってくれない。純情そのもので俺は嬉しくなった。やがて暗くなり映像が天井に映り始めた。ナレーションが流れているが、俺の耳には殆ど入っていない。唯々真理子ちゃんの横顔を盗み見し、吐息に聞き入っていた。 天体ショーが終わり、二人はサッサと立ち上がった。が、俺は立てなかった。眩しさに目がまだ慣れない。星の瞬きではなく、真理子ちゃんの横顔に目が行っていたために、目を開けられないのだ。 「真理子ちゃん、立たせてて上げて。」という、事務員さんの声に促されるように、真理子ちゃんの手が俺の肩に触れた。一瞬、電気が走った。鼓動が高鳴り、耳がガンガンする。 車の中で、二人が作ってくれた昼食を摂った。目を合わせることができない俺としては、バックミラーの中の真理子ちゃんを盗み見するのが、精一杯だった。 「お味はどう?」と問いかけられても、正直のところ味などは分からなかった。 「すごくおいしいです。」 声の固いことは、俺にも分かった。緊張の極にある。 「どうしたの、さっきまでの威勢の良さはどこにいったの?それとも、美女二人のご馳走に感激しているのかナ?」 「まったくその通りです。のどを通りましぇーん。」 「そう言う割には、よく食べてるじゃない?」 事務員さんは俺に声をかけてくれるが、真理子ちゃんは事務員さんだけに話している。淋しい気持ちが襲ってきていた。 「あのぉ、リンゴはお好きですか?」と、初めて声をかけてくれた。どうやら、事務員さんに促されたようだ。 「はいっ。」と、思わず素っ頓狂に答えた。その答えぶりがあまりに緊張していたため、どっと皆が笑った。 時計の針は、一時半を指している。事務員さんの希望で、車の少ない方向に下りることになった。こちらの方向は初めてだった。我々のG市ではなく、S市に向かうことになる。出来るだけ長い時間のデートらしきものを楽しみたい俺としてもありがたい。真理子ちゃんの声も聞かず、すぐに走らせた。 少し行くと、小ぢんまりとした台地があった。車を止めて、外に出た。事務員さんはそこで大きく深呼吸した。真理子ちゃんも並んで、大きく空気を吸い込んだ。俺は、後ろで何とか好印象を持ってもらおうと、いろいろと考えた。しかし、何も浮かばない。気の利いた会話が浮かばないのだ。車の話だったらそれこそ何時間でも話せるのだけれど。 と、自然が俺の味方をしてくれた。山の下から吹き上げる風が、見事に真理子ちゃんのスカートを捉えた。 「キャッ!」と声を発し、片手でスカートを押さえもう一方の手で、顔を半分覆った。確かに見えた、白い物が。しかしそれはほんの一瞬のことだ。だから俺は見えなかったと答えた。 「うぅーん、見たでしょ!」と、なおも詰問された。見たと言えば、その場が落ち着きそうな気がしたので、実は見たと答えた。 「いや、エッチ!」と、俺の予想に反して強烈に言われた。 「馬鹿ね。こういう時は見えなかったって、言いはるものよ。」と、事務員さんに窘められた。 「いや、ホントは見てないよ。だけど、見たと言わないと収まりがつかないような気がしたから。ホント、見てないって。埃が目に入って閉じちゃったよ。」 ありがとう、風さん。この後、真理子ちゃんとの会話がスムーズに出来るようになった。主に会社での出来事だったけど、主任が嫌いだという点で一致したことが妙に嬉しかった。価値観というと大げさだが、共通のものがあるということが嬉しかった。 帰りの車中では、三人とも無口だった。疲れていた。しかし、その沈黙も苦痛ではなかった。ラジオから流れるメロディーに合わせて、二人がハモっている。心地よい疲れを感じつつ、俺は車のスピードを上げることなく走った。 N橋が見えてきた。あの橋を渡ればお別れだ。このまま時間が止まってくれれば、と思わずにはいられない。ふと気付いた。いつも車の出足の遅さに苛立ち隣の車と競争していた俺が、今は全くと言っていいほど気にならない。ゆったりとした気分で走っている。勿論別れの時間を少しでも遅くしたいという気持ちはある。が、それだけではない。虚無感という言葉が、突如浮かんだ。孤独感と言い換えてもいい。 そして、スピードという危険と隣り合わせの中に自分を置いていたことに気付いた。一瞬の気の緩みも許されない環境に、自分を追い込む。そうすることで、充実感を得ていたのかもしれない。しかし今の俺は、充分に充実感に浸っている。救われている。 ありがとう、風。君のおかげで、僕は救われたような気がする。そして、 ”風よ、伝えて!“ 僕の思いを、あの娘に。 |