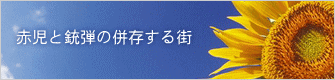
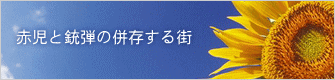
| いつもの穏やかな一日を迎えられるはずだった早朝に「コン…コン」と、遠慮がちにドアを叩く音が聞こえた。 “こんな朝早くに、何の用だ、一体。” 不快な思いを抱えて、気怠い体をゆっくりと起こした。のっそりとベッドから降りて、ランニングシャツと猿股姿では具合が悪いとばかりに、ズボンをはいた。ポロシャツもと思いもしたが、早朝なのだから勘弁してもらうことにした。この棟一番のお洒落者となっているわたしだ、変な格好はできない。正直のところ、ありがたくない風評なのだが、訳ありで演じざるを得なくなっている。 少し前のことだ。ハローワークで紹介された就職先の面接に出かける折に、バッタリと井戸端会議中の面々に出くわした。軽く会釈をして立ち去ろうとするわたしに、そうはさせじとばかりに老婆二人が立ちふさがった。満面に笑みを浮かべて、これ以上の退屈しのぎの獲物はいないとばかりに話しかけてきた。 「えっと…たしか、先月越していらした…」 「はい、山本です」 “引っ越しの挨拶をして回っているのに…” 腹立たしい気持ちになったが、グッと我慢の子で答えた。 時間が気になっているわたしは「申し訳ありません。ちと急ぎでして」と、二人の間をすり抜けようとした。 「あら、そうなんですか?」 言葉では済まなさそうな意味を漂わせるのに、その表情はまるで鬼瓦だ。とてものことに、そのまますり抜けるわけにはいかなかった。 「これから面接でして」 報告する義務など、当然ありはしない。しかし時間に追われる現在の状況を説明する上でピッタリの言葉と思ったのだが、裏に入ってしまった。 「山本さん、失業中でしたの? どちらを退職なされたの? 退職金なんか、たっぷりとお受け取りになったでしょうね?」 矢継ぎ早の質問だ。しかしわたしには、いちいち答える時間は、到底ない。 「ほんとに、申し訳ないです。お昼過ぎには戻ってきますので、またその折にでも」 平謝りに謝って、ようやくその場を逃れることができた。やれやれと思ったものの、甘かった。帰宅後に必ず話を聞かせてくれと、念を押された。 面接では思った以上の好感触で、有期契約社員としての入社が決まった。有資格者として、好印象を持たれたようだ。 ハローワークの担当者が口酸っぱく勧める、エコ検定なるものがあった。 「邪魔になるものでもありませんし、是非お取り下さい。私としては、エコ検定をお勧めします。大丈夫です、専門知識は不要ですから。問題集も出ていますし、常識問題ばかりです。こうした資格というのは、案外と再就職に有利に働くものですよ」 神妙な顔つきで頷いてはみたものの、心内では“受験だって? 何で今さら…。勘弁してくれよ”と舌打ち物だった。しかし再就職に有利に運ぶと聞くに至って、取得を決めた。 正直の所、半信半疑だったけれども、これが見事にはまったわけだ。ありがたくて、ハローワークの担当者には、感謝感謝だ。あちらに足を向けて寝るわけには行かない。 「フォークリフトの運転は…」 工場内を案内してくれる主任が問いかけてきた。わたしは嬉々として「はい、前の会社で運転してました」と答えた。 「いやあ、そうですか。それはありがたいです。それじゃ、資格証を初出社時にお持ち下さい。コピーを取らせて頂きたいので」 「免許ですか? あるとは聞いていますが、無しで運転していました」 「それじゃ、だめですね。うちの会社では、資格証がないとだめなんです。そうですか、それは残念だ。あ、でもご心配なく。山本さんにお願いしたい部署では、必要がありませんから。持ってみえたらいいなあ、という程度のことですから」 明るく笑ってくれる主任の言葉に、ホッと胸を撫でおろした。このことで採用が取り消されては、たまったものじゃない。結局、給料の締め日の関係で、四日後からの出社となった。 意気揚々と帰り着いたわたしを待ち受けていたのは、「遅かったわねえ」と、不機嫌な顔を見せるお隣さんだった。 「お昼過ぎって聞いてたけど、今、何時かしら? うちの時計では、もう三時を回っているんだけど」 「あぁ、失礼しました。ありがたいことに、就職が決まりまして。会社内を見学させてもらったら、遅くなってしまいました。お待たせしてしまいました」 “なんで謝らなきゃならんのだ。” と思いつつも、へこへこと何度も頭を下げ続けてしまった。そんなわたしとお隣さんの声に気が付いたのか、ぞろぞろと集まってきた。まったく、暇な御仁ばかりのようだ。結局のところ、二時間ほど質問攻めにあった。 六年前に離婚してバツイチであること、子どもたちとは手紙のやり取りはあるけれども、今流行りのメール交換はしていないと話した。そして三年ほど前に心臓を患い、今年の春からペースメーカーのお世話になっていることも、話してしまった。 「手紙だなんて、今どき珍しいわね」 「あたしなんか、孫がメールをくれるって言うから、携帯電話を買わされちゃったわよ。それも、孫の分まで」 「あなたもなの? あたしもよ。スマートホンとか言うのを、買わされちゃったわ。同じ会社だとお安くなるから、孫も買い換えたいって。二台よ、二台。ほんと、ちゃっかりしてるわ」 「だけどさ、あれ、良いわね。ジー、ジー何とかって言う、迷子になってもさ、位置が分かるんですって。『認知症になっても、あたしが見つけてあげるから…』なんて、孫が言ってくれてさ」 すっかりと、孫の自慢話になってしまった。 「山本さんは、どうなの? お孫さん、いらっしゃるの?」 「いえ、わたしの所はまだでして。わたしも晩婚でしたが、子どもたちも晩婚になりそうです」 「あらそうなの、それは淋しいわね」 結局のところ、わたしのプライバシーは丸裸にされてしまった。そしてその結論が「キチンとした方ねえ。行く行くは、自治会の役員さんね」と、なり「この棟一番の、お洒落さんよ」と決めつけられてしまった。ネクタイを締めているからということで、お洒落しているということになってしまった。 前のアパートでは、熱い夏の盛りなどは猿股一枚で過ごしていた。窓を全開にしドアも開けて、風の通り道を作っていた。だから部屋の中は、外から丸見えだ。しかし何も気にすることはない。隣の住人も上下階の住人も皆、男ども皆がそのスタイルだったから、それが当たり前となっていた。ここだけの話、夜などは、♪風に吹かれて、ぶーらぶら♪状態だ。実に気持ちが良く「良くぞ男に生まれけり」と、男の特権を満喫していた。 それがここに移り住んでからは、行儀良くせねばならない。もう一度前のアパートに戻りたいと思わぬでもない。しかし、低家賃だから、と己を納得させている。 「どなた? どなた?」 二度ほど声を掛けてみたが、何の返事もない。やむなくロックを外して開けてみた。やはり、誰も居ない。ドアの郵便受けに回覧板を見つけた。、どうやらお隣さんのようだ。いちいちドアをノックしなくても良さそうものなのに、と少々苛立った。 確かに「互いに声を掛け合いましょう」と、自治会で決議されはしたけれども。大げさなことをと思いはしたが、役員連の真剣さに気圧されて賛成してしまった。しかしそんなことにいちいち目くじらを立てていては、この団地で平穏な生活など出来はしない。隠忍自重、穏忍自重と、己に言い聞かせている。 兎にも角にもざっと回覧に目を通して、廃品回収の日付を確認した。再来週の土曜日となっている。そういえば、廃品回収では苦い思い出がある。何が原因だったかは覚えていないけれども、些細なことからだったと思う。その場を取り仕切っていた男と口論となり、廃品の回収を拒否されてしまった。他の人の取りなしで、持ち帰る事態は避けられたけれども。 以来、持ち出すのを止めた。おかげで大量の新聞やらチラシがたまってしまった。ちり紙交換車のアナウンスが聞こえた折には、何をおいても外に飛び出して探したものだ。ここではトラブルを起こさぬように、言動には気を付けねばと己に言い聞かせている。 「回覧は早く回してください」 と、うるさく言われている。その足で次の部屋へと回した。ドアをノックすべきか? と迷ったけれども、出てこられては面倒だと郵便受けに差し込んで引き上げた。 明るいとは言っても、まだ六時ぐらいだ。それなのに向かいに立つ棟の窓で、白い洗濯物が風に揺れている。どこの洗濯機なのか、ゴーゴーと音も聞こえてくる。年寄りの早起き? と思ったが、この団地の中には、若夫婦や中年夫婦も住んでいるはずだ。 わたしの居るこの五棟だけが、姥捨て山のようにひっそりと年寄り連が居る。いや待て。ひっそりと、だと? そんなことはない。毎日毎日どこかしらから、幼い子供たちの歓声が聞こえてくるではないか。わたしにしても毎日の家事には、CDの音楽を流している。 そうか、このことも、あの「お洒落さん」に関係しているのかも。流す音楽では、昔懐かしいエルヴィス・プレスリーや、六十年代のロックミュージック等が多い。 友人の一人に「変な奴」と言われるのだけれども、どうにもビートルズが好きになれない。 エルヴィス・プレスリーに心酔していたわたしにとって、プレスリーとビートルズの初めての出会いの場でジョンがとった無礼極まりない態度は、到底許せるものではなかった。勿論、日本の歌謡曲も好きで、たまに聞いている。ど演歌であるぴんからトリオの「女の操」も聞かなくはない。 ましかし、その喧噪も、夜の九時までのことだ。NHKのニュース番組が始まると、とたんに静かになる。十時ともなると、すべての窓が暗くなる。物音一つなくなる。灯りが点いているのは、私の部屋ぐらいだろう。しかしそれからが、私にとってはとっておきの時間なのだ。 夕刻の六時過ぎに仕事から帰り着くと、先ずはトイレに駆け込む。便器に座って大きくため息を吐いて、今日も無事に帰り着いたと安堵する。さあそれから、ひと仕事だ。まずは弁当箱を取り出して、スポンジをたっぷりと泡立たせてゴシゴシと洗う。そこまでしなくてもと思いはするが、一人住まいの身では病が一番怖い。やれ熱が出た、腹が痛いと騒いでみても、助けてくれる者は誰一人居ないのだから。全てを一人で完結せねばならないのだ。ゆえに必然、予防に心がけねばならないのだ。 そうだった。ゴシゴシの前に、水切りかごの中を空にせねばならぬ、食器類の片付けをせねばならぬ。朝と夕では、使用する食器類が違う。朝をパン食にしているわたしだ、コーヒーカップやらスプーンを片付けねばならない。夕食の食器類と同時にと考えないでもないが、一度にたくさんは洗いたくない。それに洗い桶への入れっぱなしは、どうにも性に合わない。 外から戻った途端、ブルッときてしまった。すぐさまベッドに逃げ込むと、あっという間に眠りについた。 「ピュルルル、ピュルルル」 玄関先に置いてある電話機の呼び出し音が、けたたましく鳴り出した。電話がかかるとは、珍しいことだ。時計を見ると、もう十時近くを指している。寝坊をしてしまったと、慌ててベッドを出た。もういい加減起きなくてはと、今度は素早くベッドを出た。 しつこく鳴り響く電話に出ると、「はい、どちらさん?」と不機嫌に答えた。 「あぁ、やっと出てくれたね。だめだよ、田中さん。こっちも忙しいんだからさ」 こんな失礼な言い方をされては、こちらも黙っていられない。 「そちらこそ失礼でしょ! わたし田中じゃありませんから。番号違いですよ」 「何言ってるの、田中さん。昨日、女の子が電話した時には、出てくれたじゃないの」 と、相手は引き下がらない。 「あぁ。だったら、やっぱり間違いだ。わたし、昨日は仕事で留守でしたから。それじゃ忙しいので」 受話器を置こうとすると「ちょ、ちょ、ちょっと、待って。あんたがそういう態度に出るのなら、結構だ。こっちもね、それなりの対応を取らせて貰うから」と、口調が少しぞんざいになってきた。 「それなりと言われてもですね、わたし田中じゃないですから。それじゃこれで」 「待てって、言ってんだよ、こら! じゃ、なんて名前だよ、こら!」 突然、言葉がやくざ調になった。 「ま、いいや。あんたが田中じゃないって言い張るんなら、それでもいい。とにかく、料金を払ってくれや」 柔らかく落ち着いた声が、突然にドスのきいた声に変わった。 「聞こえてるんかい! 返事せんかい!」 豹変したその声が耳に入ると、高飛車な口の利き方をしてきたことがまずかったのではないかと、急に不安になった。受話器を持つ手がわなわなと震え、足もガクガクとしてきた。 「り、料金って、なんのことでしょう」 わたしの声がかすれ気味になってきた。心臓の鼓動が、耳にガンガンと響き渡る。 「なんの料金ですか? だと。とぼけちゃ困るな、佐藤さん。いや、田中さん。アダルトサイトで動画を観ただろうが」 「あのぉ、わたしじゃないと思うのですが。それって、インターネットとかですよね。わたし、もう六十を過ぎてますし、それはやってませんので……」 これで納得してくれるかと思ったのだが、相手はかさにかかって恫喝してきた。 「それじゃ、なにかい? あんた、パソコンなんてのは見たこともないとでも、言うんかい、こら!」 「い、いえ。パソコンは、あります。息子がくれましたので。『買い換えたから、古いのをやるよ』って、ですね。でも、埃をかぶってます」 つい余計なことを、言ってしまった。しまった! と思っても、吐いた言葉は取り消せない。 「ほら、みろ。持ってるだろうが、田中さんよ。嘘はいけないよ。一つ嘘を吐くとね、際限なく吐き続けなくちゃならないんだよ。そんなこと、出来るわけないよね」 猫なで声で、優しく諭すように言ってきた。 「ほんとなんです、インターネットはやってないんです」 必死の思いで、反論した。弱々しい声ではだめだ。もっとはっきりと説明して、キチンと分かって貰わねばと、己に言い聞かせた。しかしそう思えども、震え気味の声が出るだけだった。 「分かった、分かったよ。信用してやるよ、田中さん。パソコンは使ってないんだね。けどさ、携帯持ってるでしょ?」 「携帯電話ですか? はい、持ってます」 「じゃさ、たとえば、お子さんとは電話で話してる? 正直に言ってよ、嘘はだめだよ」 相手の静かな声に、わたしの興奮状態も少し収まってきた。次第に手の震えも収まり、胸の動悸も平常に戻り始めた。 「い、いえ。子供たちとは、電話では話していません」 「うん、うん。そうだよね。、電話では話なんかしないよね、今どきは。正直に答えてくれたね、いいことだよ。でもさ、メールのやり取りぐらいはしてるでしょ?」 この時に、相手が何を言わせたいのか、気付くべきだった。しかし蜘蛛の巣にかかった蝶のように、もがけばもがくほど身動きが取れなくなっていった。 「は、はい。子どもやら友人たちと、ほぼ毎日メールのやり取りはしています」 つい見栄を張ってしまった。月に一度あるかないかの、メールのやり取りだ。 「田中、…じゃなくて、ま、いいや。この歌、覚えてる? ♪だよねー、だよねー♪」 突然に相手が歌い出したのには驚いた。と同時に、腰にピリピリとした痛みを感じ始めたわたしは、思い切って告げた。 「すみません。ちょっと腰が…。椅子を持ってきますので」 受話器を置いて離れたところ、電話を切られると思ったのか、またぞんざいな言葉に変わった。 「こら、田中! 勝手なことするな! 聞いてるのか、こら! 返事しろよ、こら! 」 がなり立てる声が、玄関で響いている。外にまで聞こえはしないかと、慌てて受話器を取った。 「ごめんなさい、どうも。この歳になると、すぐに腰に来ちゃうものですから」 「あんた。メール、やってるよね」 「はい、やっております」 「その携帯で観たんだよ。メールってのは、インターネットに繋がってないと、だめなんだよ。思い出したかい?」 謀られた! と思ったときには、もう遅かった。メールの仕組みが分かっていないわたしでは、何をどう言ってもインターネットが使える状態にあることになってしまった。 「でもですね。先ほども言いましたが、六十過ぎなんです、わたし。もう、そんな色事とは縁がないんです。それに糖尿病を患ってますし、お分かり頂けましたでしょうか」 「なんだと、こら! 六十過ぎたからアダルトは観ないだと。糖尿で、おチンチンが勃たないだと。寝ぼけたことを言うな、こら! だからこそ、観たんだよ。ほんとに勃たないかどうか、確認したんだろ? 四の五の言わずに、黙って払えばいいんだよ。それとも、これから家まで押しかけようか。『アダルトに狂ったエロ爺いです!』って、触れ回ってやろうか。ええ、どうなんだよ、こら!」 「そ、そんなこと困ります。あたし、真面目一本で通ってるんです。やめてください、そんなこと。ほんとに、お願いしますから」 何を言ってもだめだった。わたしが話すこと全てに、逆の意味を与えられてしまった。 「だろ? だったら素直に振り込みなさいよ。こっちだってね、事をさ、荒立てたくないわけよ。実を言うとね、もうオタクの家に行ってるのよ。長々と電話しているのは、何でだと思う? 分かるかな、ぼくの言ってることが」 ギョッとした。言われてみれば、どれ程の時間が経ったのか…。確かに長々と話している。本当に来ているのだろうか。まさかとは思うけれども、ドアの向こうに立っているのでは…。ドアノブに手を伸ばしかけて、すぐに引っ込めた。万が一に居るとしたら、開けた途端に入り込まれてしまう。ぶるぶると、手足だけではなく、体全体が震え始めた。陽が射し込んでいるのに、部屋が冷たく感じられる。早くこの場から逃げ出したくなった。 “このまま電話を切ろうか…” とも考えはした。しかしその後に、何かもっと恐ろしいことが起きそうで出来なかった。 「だからさ、悪いことは言わないって。素直に金を払いなさい。ね、田中さん」 「ですから、あたし、田中じゃありませんて。人違いなんですよ。ホントですよ」 弱々しくか細い声で答えた。相手に聞こえているのかどうか…、自分自身にすら聞こえない声だった。 「いいんだよ! 名前なんか、どうでもいいんだよ! お前が払ってくれさえすれば、それで万事めでたしめでたしなんだよ! なあ、佐藤さんよ。いいかげん、往生しなよ。俺だってさ、暇じゃないんだから。まだあちこちに、電話しなくちゃいけないの。佐藤さんよ、あんたも疲れたろ? ここらでさ、楽になろうや」 相変わらず、無茶苦茶な論法で押してきた。いつの間にか田中という名前が佐藤に変わってしまい、わたしではないことが明白となっているにも関わらず、わたしに払えという。 「よし、分かった。それじゃ、こうしようか。金額をね、減らしてあげるよ。依頼主さんに交渉してあげるわ。今ね、三十一万五千円で来てるの。それをね、丁度三十万円にしてあげるわ」 椅子に腰掛けているせいか、少し興奮状態が収まりつつあった。相手の話の矛盾点が、分かるようになっていた。そして声にも、少しながら力がみなぎってくるように感じた。 「ですから、何度も言いますが、人違いなんです。それにわたし、何度も言いますが、糖尿病なんです。そちらの方は、まるでダメなんです」 「分からん奴だな、お前も。よし、分かった! 二十九万にしてやろう。どうだ、大サービスだぞ。えっと…中、じゃない。佐藤でもない…えぇい! 誰でもいいや。とに角、振り込めや」 「そ、そんな、あなた。無茶苦茶ですがね、そんなこと…」 「いいかげんにしろ、こらっ! 幾らなら払えるんだよ、こらっ!」 「幾らならだなんて、あなた。ほんとに観たものなら、三十が四十でもお支払いしますよ。けどですね、ほんとに観てないんですから。ほんとに、あたしじゃないんです」 「よし分かった。お前がその気なら、こっちも最終手段に出るよ。もう良い、もう良いよ。謝っても、だめだから。払います、振り込みますって言っても許さんから。待ってろや、これから行かせるから。といってもだ、俺だって鬼じゃない。お前がな、頭を下げてだ、これからすぐにも振り込みますって言うんやったら、考えんでもない。どうや? どうする? 振り込むか?」 男の「振り込む」という言葉に反応するかのように、冷蔵庫の側面に貼ってある広報紙に目がいった。 [振り込め詐欺に注意!] 昨年の暮れに受けた講習を思い出した。自分に限ってそんな事態にはならないさ、と高をくくっていたわたしだった。平日の夜と言うこともあり、欠席するつもりでいた。思いの外に仕事がきつく、体を十分に休めたなければ、翌日を休む羽目になる。しかしお節介な隣人に誘われて、渋々参加した集会だった。 「他にも、架空請求というものがあります。覚えのないことでの請求には、決して応じないように。まず警察に相談してください」 “そうだ、そうだった。相手の言うなりになっちゃだめなんだ。” 冷静さを取り戻したわたしは、意を決して「警察に連絡します。そちらさんの会社名を教えてください」 と、震え気味の声できっぱりと言い切った。受話器を持つ手が、激しく震えた。心臓の鼓動も、これ以上ないという程の早鐘状態になった。 “しっかりしろ! ここが正念場だぞ” ともすれば弱気になりがちな心を叱咤し鼓舞して、震える手をもう一方の手で抑え付けた。 「なんだと、こら! ふざけたこと言うと、いわすぞ、こら! どこの警察だよ。新宿か、渋谷か。そこらの警察には話が行ってるんだよ、こら! 相手になんかされねえよ。聞いてんのかよ、こら!」 何度も「こら!」と脅しにかかってきた。そのたびに体がビクリと震えはしたが、警察という言葉を口にしたとたん、慌てふためく男の様子が手に取るように分かった。恐怖感がとれたわけではないが、いくぶん冷静になれた。 「とにかく、これから警察に行きますから」 わめき散らす相手の声を遮り、叫ぶように大声で告げて、受話器を置いた。いや、置こうとした。しかし、手が、指が、張り付いたように固まっている。一本ずつ指を外して、ようやく置けた。手にはじっとりと汗を掻いている。口中もひからびて、のどがひりつく感じだった。 “待てよ。警察と言ったら、新宿とか渋谷とか言ってたな。東京じゃないか。なんだ、こっちの住所は分かっていないじゃないか。何が人を向かわせてるだ……。” 安堵感が一気に広まった。そしてあの会場でのことが思い出された。 「大体がですね。かけた相手については、何も知らないことが多いんですよ。適当な番号に電話をかけて、相手が老人だったり女性だったりした時に、脅しをかけるんです。良いですか、皆さん。決して、お名前を名乗らないように。住所もだめですよ。そうそう。初めはね、若い女性の場合もあるんです。荷物を届けたいので、住所を教えて下さい、とかね。若い女性との会話が楽しいからとスケベ心を出したら、相手の思うつぼですよ」 時折笑いを取りながら話す警察官で、会場は和気あいあいとした雰囲気だった。そんな中、会場が凍り付いたのは、実演の舞台が始まってからだった。 演者の実に巧みなトークで、錯覚に陥りそうになった。一歩引いた立場での観客である我々だからこそ、冷静に聞いていられるものだった。もしも一人居る部屋にかかった電話に対して、警官が言うような対応ができるかどうか…。皆が黙りこくってしまった。 「一人だと、判断がつきませんね。これが大事なことですよ。携帯電話の番号が変わったよと言われたら、以前の番号にかけてみて下さい。案外に嘘なんです。万が一に銀行に行ってしまったら、受付の女性に声をかけてください。分かります、急いでいますよね。でもね、一分二分のことですから。振り込みのことで、相談して下さい。間違っても、ATMは使わないように。お爺ちゃん、若い女の人とお話しできるんですから。お婆ちゃん、男性の行員とお話ししましょうね」 ひとしきり会場の笑いをさらった後、真剣な顔つきで付け加えた。 「いいですか? 三種の神器ならぬ、三つの危機があります。ATM・還付金・振り込む、この三つですよ。そしてね、やってはいけないこと。ひとつ、自分から名乗らないこと。ふたつ、○○ちゃんかい? と名前を言わないこと。最後に、おかしいなと思ったり、相手から脅しをかけられたら、すぐに警察に連絡をしてください。こんなことぐらいで…なんて、決して思わないでください。あなたが連絡をしてくれたら、他の人が助かるのです。隣にお座りのお爺ちゃんお婆ちゃんが、被害に遭わずに済むんです。ねえ、皆さん。これだけ我々がお話ししても、被害者が出ているんです。お帰りになった途端、いえ、この会場を出られた途端、今日の、今のこの話を忘れてしまわれるんです。良いんですよ、忘れても。細かいことをね、一々覚えてられません。そこでお帰りの時に、チラシをお渡しします。今日の話の要点が書いてあります。このチラシをですね、電話機の傍に置いておいて下さい。携帯電話で話す時には、このチラシが見えるところで話して下さい。そして時々、このチラシに目をやって下さい。お願いしますね。このぼくに、電話を下さい。夜でも良いですよ、誰かが応対してくれますからね。はい、それじゃ、お疲れさまでした」 へなへなとその場に座り込んでしまい、どっと疲れが出てきた。 “終わった…。勝てた、勝てたぞ。ハハハ…。案外に簡単じゃないか。警察って言ったら、慌ててたじゃないか。なにが押しかけるだ、いい加減なことを” しかし途端に、大きな不安が襲ってきた。 “ひょっとして…電話番号から住所を調べられたら…” “いや、そんなはずはない…さ。個人情報はうるさく規制が…” “しかし…個人情報流失云々と、しょっちゅうニュースで…” 慌ててチラシに書かれている警察署に電話をかけた。担当者の名前を告げると、暫く待たされた。一分とかかっていないと思うのだが、十分にも二十分にも感じられた。一秒ずつ動く時計の長針が、やけにゆっくりな動きに見えた。居ても立っても居られぬ思いに駆られた時、「お待たせしました」と、声が耳に入った。 「あ、あ、あの…」 「落ち着いて下さいよ。そうですね、まず深呼吸しましょう。それからで結構です。最初は、お名前を伺いましょうか?」 ふーはーと、大きく深呼吸をした後に「はい、山本、と申します。実は、先日、振り込め詐欺の実演を観た者なのですが…」と告げた。 「はい、分かりました。で、どうされました? 電話がかかってきましたか?」 「そうなんです、かかってきたんです、今」 「大丈夫です、安心して下さいね。どんな話でしたか? 相手は、男でしたか? 女性でしたか? あ、ごめんなさい。一つ一つ聞きましょうか。男か女か、教えて貰えますか」 「男です、男。覚えのないことで、金銭を要求してきたんです。わたしね、パソコンはやっていないんです。インターネットは知っていますけれど、電話はありますよ。でも、使い方が分からないんです。。あ、いや、メールはしているんです。でも、パソコンではなくて、その…分かりますか? わたしの言っていることは…」 落ち着こうとするのだけれども、どうしても早口になり、話もあちこちに飛んで支離滅裂になってしまう。 「大丈夫ですよ、山本さん。パソコンでのインターネットはしていない。携帯電話でのメールぐらいものだ、そういうことですね?」 さすがに警察だ、言わんとすることをすぐに理解してくれた。 「今朝突然に電話がかかりまして、男からでした。『田中さん、金を払ってくれ。』とです。えーっと、何だったか…そうそうアダルトを観たとか何とか。名前も違いますし、先ほど言いましたとおり、インターネットはやっておりませんし。そしたら携帯電話で観たんだと言う始末で。警察に言うぞ、と言いましたら、警察とは繋がりがあるから通報しても無駄だなんて言い出しまして。でも、チラシを見て、思い切ってかけたようなわけでして。おわかりですか、こんなことで」 すると突然に、ケタケタと笑い声が耳に飛び込んできた。 「いやいや、失礼。それは賢明でした。お名前を間違えてましたか。山本さんだと名乗られなかったんですね。それで結構ですよ。大丈夫、立派な対応でした」 “待て待て。名前は…言わなかったはずだけれど…” そんなわたしの不安を見透かしたように、「もしもし、山本さん。万が一にですね、お名前が相手に分かってしまったところで、だから何なんだ! ということです。ご心配はありませんよ、大丈夫です。それと警察はね、そんな輩と通じてなんかいません。テレビのドラマなんかでそういった筋立てがありますが、面白可笑しい話を作っているだけですから。ご心配なく。少なくともわたし共は、決してありません。ご安心下さい、ほんとに大丈夫です。」と、力強く否定する警察官の言葉が、頼もしく聞こえた。 「そうですね。最寄りの交番に、連絡をしておきます。何かあったら、一一〇に電話してください。山本です、と言って頂ければ、すぐに駆けつけさせますよ。大丈夫、そんな事態は、まずもって起きませんから。それでも、駆けつけさせます。何ごともないのが一番です。ね、大丈夫ですよ。はい、今日はありがとうございました」 警察官が力強く発した「大丈夫です」と言う言葉に安堵感を覚えた反面、何度も繰り返されたその言葉の裏にあるものが、何か他意のあるようにも感じられて、多少の不安を覚えさせずにはいかなかった。 “ドラマの話が出たぞ。そういえば、暴力団に便宜を図ったという刑事のニュースを見たことがある。少なくともわたし共は、とはどういう意味だ。いや、言葉通りさ。そうだよ、新宿とか渋谷とか言ってたじゃないか。そうさ、そうだよ。昔は栄えていた繁華街も、今じゃ閑古鳥が鳴いてるって言うし。暴力団も、いなくなったんじゃないか?” 気付くと、何をすることもなくテレビに見入っていた。画面の中で何かが動いていることは認識しても、それが人間なのかあるいは物体なのか、まるで判別できない状態だった。それからどのくらいの時間が経ったのか、猛烈な空腹感に襲われて我に返った。 “あぁ、もうお昼を過ぎてるじゃないか” のっそりと立ち上がりはしたものの、なにをする気にもならず、先日買い置きしておいた菓子パンに手を伸ばした。いつもならお腹が膨れてくるのだが、今日はまだ空腹感は収まらない。 “今日は特別に、喫茶店で食べるかな” 実のところ、警察を疑うわけではないが、万が一ということもある。出張ると言っても、すぐにとは限るまい。どれ程の時間がかかるのか…。その間、どう対処すればいいのか。 “留守だと分かれば、相手も諦めるだろう。今は法律もあることだし、張り紙やら隣近所への嫌がらせもしないだろう。とに角部屋に居ちゃだめだ” 居ても立ってもいられなくなったわたしは、戸締まりをしっかりとして外に出た。今にして思えば、電話なのだから、早々に切ってしまえば良かったのだ。再度かかつてきた折りにこそ、警察云々で良かった筈だ。いやいや、すぐに部屋を空にするのも良しだ。 それを長々と付き合ってしまった。案外のこと、相手との会話を楽しんだのかもしれない。だとすれば、相手もいい迷惑だったろう。電話など、いや会社外で人と会話をするなど、何日、何ヶ月ぶりのことか…。そう思うと、あれ程煩わしく感じた隣近所との会話が、それなりのものに思えてくる。思わず苦笑してしまった。 外に出てみると、ポカポカとした暖かい日差しがあった。時折吹いてくる風には少しの冷たさを感じたけれども、身を縮込ませる程でもない。打ち沈んでいた気持ちが、少し収まってきた。 車の行き交う通りに出ると、いろいろの音やら声が、わたしの耳に飛び込んできた。交差点で止まった車の運転手がわたしを睨みつけているように感じられて、慌てて下を向いた。 “ま、まさか…そんなことはない。気のせいだ、きっと” 顔を上げると、何ごともなかったかのように、車が走り出していた。 公園にさしかかると、子どもたちの歓声が聞こえてきた。 「だめえ! それはみいちゃんのブランコ!」 「ばあーか。はやいものがちだよーだ」 幼稚園児らしい二人が、先を争ってブランコに向かった。三台あるのだが、残りの二台は小学校高学年らしき女子児童二人が、交互に高くまで揺らしながら、ハイタッチを繰り返している。 「順番に乗りなさい。お姉ちゃんたちの邪魔にならないようにね」 母親らしき女性が、コニコと声をかけた。その声に呼応するかのように、半べそをかいている女の子に「お姉ちゃんたち、もうあきたから」と声をかけて、女子児童二人がブランコを降りた。 少し離れたその横では、お父さんであろう男相手に、ボール蹴りに興じている男の子がいた。年の頃、三、四才だろうか。ころころと転がるゴムボールを、一生懸命に追いかけている。そして追いついたところで、声を上げて「シュート!」と、打とうとする。しかし決まって、空振りしている。何度か繰り返す内に、足がボールに当たった。 転がりはしたものの、二、三メートルほどで止まってしまった。しかしその子は追いかけるでもなく、離れた父親が打ち返すのを待っている。 「もう一度シュートしてごらん。ほらほら、頑張れ!」 父親が声をかけると、やおら男の子が走り出した。今度はうまく一度でボールに当たったけれども、残念なことに方向が悪く、父親からは更に離れた場所に行ってしまった。その場に立ち止まった男の子は、「まだけるの?」と言わんばかりに父親を見やっている。さすがに今度は、父親がボールに向かった。 「ほーら。タケくーん、行くよ!」 優しい声をかけながら、軽くボールを蹴った。男の子は、嬉々としてボールに向かっていく。その額に光る汗が、わたしにはことさら眩しく見えた。 “可哀相なことをしてしまった” 己の父親としての自覚のなさを後悔した。子どもが嫌いだったのではない。可愛くなかったわけではない。人並みの愛情は、持っていたつもりだった。ただ、その表現の仕方が分からなかったのだ。どう接すればいいのか、分からなかったのだ。己の心のゆとりのなさが、子どもとの時間を作らせなかったのかもしれない。 何と言うことはなかったのだ。1日をかけてどこかに出かける必要も、一泊の旅行を計画する必要もなかったのだ。ほんの一時間でも三十分でも、この親子のように公園でのボール蹴りに興じれば良かったのだ。ブランコ遊びに興じても良かったのだ。手をつないで川縁を散歩するだけで良かったのだ。日々の中に、子どもとの少しの時間を作れば良かったのだ。 “幼い時は、母親の方が良いんだ。大きくなって、色々の悩み事を抱え始めた時が、父親の出番なんだ。” 勝手な理屈を作り出して、日々の家庭の雑事から逃げてしまっていた。子どもに捨てられたのではない。わたしが、あの時、子どもたちを捨ててしまったのだ。 ベンチに腰掛けていたわたしの足下に、ボールが転がってきた。子どもが、じっとわたしを見ている。自分が取りに行くべきか、それとも父親に任せるべきか、……逡巡しているように見えた。その純真な眼差しで見つめられていると、気恥ずかしさを覚えてしまう。 「行くよー! 坊ーや」 わざと、大きな空振りをした。とたんに、ケタケタと大きな笑い声を上げながら、手を叩いている。 「よーし。今度こそ、行くよー!」 軽く蹴り出したボールは、うまく男の子の足下に転がっていった。満面の笑顔でボールを手に取った男の子は、うんうんと大きく何度も頷いてくれた。そして父親の「ありがとうございまーす!」の声が、さわやかに耳に届いた。 公園の木々の陰が、少し長くなってきた。子どもたちはすでに家路に就いている。しかしわたしは、中々腰を上げる気にならなかった。もう、不安や恐れの気持ちはない。いつのまにか消えていた。子どもたちの余韻に、もう少し浸っていたかったのだ。 入り口に設置してある時計が、四時を指している。 “そうだ。今日は、眼科検診だ。その為に会社を休んだのだから” 午前中に済ませる予定が、あの電話で狂わされてしまった。慌てて通りに出ると、先ほどより車の往来が増えたように見えた。信号待ちの車も多い。チラリとわたしを一瞥するドライバーも居たが、すぐに視線が外れた。 買い物袋を下げた中年女性と老婆が、向こうから歩いてくる。狭い歩道を、二人並んで歩いてくる。このままではわたしの歩く道がないと、少々不安な思いがでてきた。しかしそれも、杞憂に終わった。並列に見えた二人だが、同列ではなかった。遠近がうまく分からないのだ。それもあって、眼科検診に行くのだけれども。 四時半からの受付では、五、六人の患者が外で待っていた。自動ドアの開くのももどかしく、せわしなげに入っていく老婆が、床に敷いてあったマットに足を取られてしまった。後に居たわたしは、思わず「危ない!」と声を上げて手を出した。しかしわたしが手を出すまでもなく、前列の中年女性が振り向きざまに老婆を支えていた。 ところが「後ろの人が押した!」と、とんでもないことを老婆が言い出した。周囲の冷たい視線が一斉にわたしに注がれたが、受付の看護師が見ていてくれて疑惑が晴れた。 「とんだ災難でしたね。ま、お年寄りのことですし、勘弁してやってくださいな」 中年女性の話がなかったら、いつまでもわたしの怒りは収まらなかっただろう。 「もう一度、瞳孔を開く目薬を差しますね」 マスク姿の看護師が寄ってきた。愛くるしいその目に焦点を合わせようとした途端に、ジイと目に刺激が走った。看護師の「滲みました? ごめんなさい」とのすまなさそうな声に、心打ちで舌打ちしつつも、うんうんと頷くより他なかった。 『目を開けよ!』 突然に神の啓示が降りた。恐る恐る目を開けると、そこは眩いばかりの、全てが白く輝く金色の世界だった。正面には和やかな笑みを称えられた菩薩様が、そして隣には慈悲深い笑みの観音様がおられる。私の横には蓮の葉が群生しており、その葉の上にお地蔵様たちが鎮座されている。その奥には緑の樹木がそびえ立ち、爽やかな風を送ってくれている。 「山本さん、こちらにどうぞ。眩しかったら、閉じてて良いですよ。あらあら、手が冷たいですね。外は寒かったですか?」 目を閉じたわたしの手を取り、診察室前へと連れてきてくれた。何という心優しき看護師、いや天女様か。その昔天女様の羽衣を隠したという不心得者がいたけれども…いやいや、その心内、良く分かる。いっそこのまま道行きを、と思わせる優しい天女様だ。 「どうです? 目を開けることは、できますか? 眩しかったら、良いですよ。はい。それでは、ここで待ってて下さいね」 確か壁際に長椅子のある、狭い場所だったはずだ。四、五人が腰掛けられるのだが、皆それぞれに互いのテリトリーを主張しあうので、座るのは精々が三人止まりだ。看護師たちも心得たもので、それ以上は呼び込もうとはしない。 隣は検査室になっていて、何やら機械類が七台ほど並んでいる。順番に移動をしていけるように、横一列だ。そしてその向こう側で、視力検査をやってくれる。こちらは二台ある。大体が、ほぼ満席だ。 「お待たせ、お婆ちゃん」 「早よして貰わんと、どうにもならんぞ。みんなでお昼を食べることになっちょるのに」 何という毒々しい言葉を吐く婆ぁだ。ひょっとして、先ほどのわたしを陥れようとした老婆か? 目を開けることができたなら、ジロリと睨み付けてやるものを。 「こんなに度の強いコンタクトって……」 「ごめんなさい。お友だちのレンズを、ちょっと借りてます。黒板の文字が見にくくて。前の方の席に行くの、嫌だったから…」 医者の言うことを聞かぬ小娘め、私の娘なら怒鳴りつけてやるものを。少しは医者に対する畏敬の念を持てないものか。憤慨するわたしだったが、まさかこの後にあのようなことになるとは、思いも寄らぬことだった。 「はい、山本さん。お入りください」 薄暗い部屋の中からお出でお出でと手招きする女医先生、まさしく女神様だ。眩しかろうと灯りを落としていてくださる。ありがたいご配慮だ。この部屋では、眩しさも感じない。はっきりと女医先生を目にすることができた。 三十代後半だろうか。糊の利いた白衣が、実に似合っている。メリハリの利いた顔立ちで、聡明さがうかがい知れる。確かに、美人だ。かかりつけ病院の医師が「あそこは美人の女医さんですよ。」と耳打ちをしてくれたが、嘘ではなかった。 「山本さんは、糖尿病のこと、知っていますね。合併症が恐いですからね。はいそれでは、眼底検査をさせてもらいますよ。大丈夫ですよ、なにも怖いことはありませんからね。光を当てて、中の様子を見させて貰います。眩しいでしょうけれど、辛抱してください。まばたきしたくなっても、できるだけ我慢してくださいよ」 実に優しく低い声で囁きかけられると、目の中をのぞき込まれるという恐怖感も薄らいでくる。しかし実際は、そんな生易しいものではなかった。眩しさを通り越して、痛みすら走った。まばたきをしようとすると、必ず「我慢して、我慢、我慢!」と、声が飛ぶ。できるだけじゃなかったの? 先生。はからずも涙が出ると、今度は「男でしょ! 泣かないの!」と、又もや叱咤の言葉が飛んできた。泣いてるのじゃないんです、先生。目が乾くから出てくる生理現象だと思うのですが。 「あぁ、白内障ですね。これは、手術しかありません。とりあえずお薬で進行を抑えますが、それで治ることはありませんから」 いとも簡単に手術だと仰る。治らないと、冷たく仰る。わたしの都合など、一切聞かないのですか、先生。分かったぞ、そうだった。医者という人種は、総じてサドなのだ。分かっていたはずなのに、歯科医で思い知らされていたはずなのに。見目麗しい女医先生のお姿に、見事に……。 「はい、もう結構ですよ」 あの天女様に促されて退出した。別室に移されて、「詳しい説明をしますね」と、貫禄十分の看護師さんと相対した。その甲高い声に、つい薄目を開けたのだが、見なければ良かったかもしれない。 「あのですね。眩しいんですよ、普段でも。室内から外を見るとですね、目を開けていられないんです。それに、遠近感もおかしいようで。先日の視力検査では、二重どころか四重いや六重にも見えちゃいました」 医師に話すべく整理していた文言を、一気に吐き出した。 「えぇ、えぇ。それらすべてが、白内障の症状なんですよ。他に、白く霞がかかったようなことは、ありませんでした? 程度の差はありますけれど、見にくくなったこととか」 言われてみれば、白い霞かどうかは分からないけれども、確かにテレビの画面が見にくく感じることはあった。外堀どころか、内堀まで埋められた。完敗だ、手術に同意するしかなかった。 それにしても、神様。あんまりじゃないですか! これでもか、これでもか、とお責めになる。いい加減にして欲しいものですよ、本当に。 がっくりと肩を落とすわたしを、「大丈夫ですか? 山本さん。」と、あの心優しき看護師が迎えてくれた。さぞかし愛くるしい娘さんだろうと、必死の思いで薄目を開けた。しかしその目に飛び込んできた若い娘さんは……。 いや、何も言うまい、何も考えまい 魔物が恐ろしい姿をしていると、誰が言った。神が気高い姿だと、誰が教えた。 そうだ。戦国の世に、信長が舞ったではないか。 「人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり。一度生を得て、滅せぬ者のあるべきか」 受け入れねば、受け入れねば。全てを、あるがままに、と受け入れねば。この棟の住人たちとの付き合いも、恐ろしい男からの訳の分からぬ戯言も、そしてそして子どもたちの歓声も、すべてすべて、あるがままに、と。 |
| 反省会 相も変わらず、支離滅裂ですわ。 学習能力が、まるでない! それぞれのエピソードは良しとして、それらの繋がりが弱い。 短編というのは、ほんとに難しいです。 もう一度、勉強のし直しです。 でも…… どういう勉強を…… 「受賞作を、何度も読んでみろ!」 って、もう一人のもう一人のわたしが言ってます。 |